縄跳び
冒頭
縄跳びとは、一本の縄をぐるぐる回しながら跳び続ける運動。子どもの遊びからアスリートのトレーニングまで、その万能さは「縄一本で世界が広がる」とも言えるが、実際は「縄一本で足首を殴られる」経験が多いのも事実だ。
本文
縄跳びの歴史は古く、古代エジプトや中国でも遊ばれていたらしい。当時の子どもたちも「二重跳びができたらカッコいい」と頑張り、縄に足を引っかけては嘆いていたことだろう。現代では、体育の授業で「縄跳び検定」という名の拷問が行われ、「連続100回跳べないと休み時間没収」という謎ルールに苦しんだ人も多い。一方、ボクサーやアスリートは縄跳びをトレーニングに活用し、「縄を制する者はスタミナを制す」とばかりに軽やかに跳び続ける。一般人との差は、縄が足に絡まない確率にある。
縄跳びの最大の敵は「縄の長さ調整」だ。短すぎれば首絞め状態に、長すぎれば地面を叩く鞭と化す。まさに「縄跳びは縄とのコミュニケーション」という名言(誰も言ってない)が生まれる所以である。また、二重跳びに挑戦するときの周囲の視線はプレッシャーそのもの。「なぜかクラス全員が静かになって見守る」という謎の儀式が発生し、失敗すれば体育館中に響く「あー」という合唱が待っている。
結び
縄跳びの教訓? 「縄は友達」と信じつつ、足を引っかけたら「次はいけるぞ!」と自分に嘘をつくこと。そして、二重跳びができた瞬間、誰もが少しだけヒーローになれる――たとえその後すぐ絡まっても。

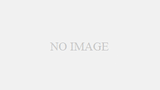
コメント