読書とは
読書とは、文字や絵を目で追いながら脳を騙して「勉強してる感」を得る行為である。紙や画面と対峙し、時に眠気と戦いながらも「教養がついた気分」に浸れる庶民の娯楽だ。
知識のシェイクスピア劇場
読書は人類が発明した最も手軽なタイムマシンと言える。300ページの小説を読めば、中世の戦場から宇宙ステーションまで瞬時に移動可能だ。ただ、現実に戻るきっかけは大抵「あ、洗濯物たたんでなかった」という日常の敗北感である。
電子書籍 vs 紙書籍 ~終わらない宗教戦争~
「紙の質感こそ至高!」と主張する人と「電子書籍の検索機能なしでは生きられない」派の戦いは熾烈だ。実際のところ、どちらも最終的には「積ん読」という共通の敵に敗北する。本棚が「未読タワー」と化す現象は、古今東西の読書家を悩ませる普遍のジョークである。
速読という幻想
「1日1冊読破!」と意気込む人々が陥る落とし穴。専門家によると、通常の読書速度で理解度を保つには1分間に300~400字が限度らしい。つまり、『戦争と平和』を電車の通勤時間で「速読」したと言い張る人は、ほぼ確実に「表紙とあとがきだけ読んだ」人種だと判別できる。
ソファーと睡魔の共謀関係
読書の最大の敵は、あの心地よいソファーと共謀する睡魔だ。「10ページだけ読んで寝よう」が最も嘘っぽい決意表明であることは、誰もが認めるところ。結局、本は顔に倒れ込み、翌朝「本の角跡が頬に凹んだ」状態で目覚める羽目になる。
積ん読の騎士道
理想の読書家像を追い求めると挫折するのは必定。大事なのは「1ページでも読めれば御の字」というゆるい覚悟だ。ちなみに、積ん読本を「将来の自分へのプレゼント」と呼べば、罪悪感が50%軽減されることが研究(※個人の感想)で明らかになっている。

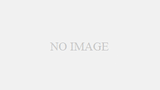
コメント