読書とは
読書とは、文字や絵を目で追いながら脳を「おっ」とさせる行為だ。紙の本でも電子書籍でも、要は「画面をスクロールするかページをめくるか」の違いに過ぎない。人類が発明した最も手軽なタイムマシンであり、同時に「積ん読」という名の家具装飾術でもある。
知識のフルコース
読書は精神のフルコース料理だ。前菜(目次)から始まり、メイン(本文)でがっつり栄養を取り、デザート(あとがき)で締める。ただし、途中で飽きて「また今度」と放置する確率は、レストランでデザートを注文する確率より高い。ちなみに、Kindleのサンプルダウンロードは「試食」に相当するが、これで満足して本編を買わない人は、スーパーの試食コーナーで夕食を済ませる輩と同類である。
ソファーの冒険家
読書家はソファーに座ったまま「冒険」できる特権階級だ。推理小説で殺人犯を追いかけ、SFで宇宙を彷徨い、自己啓発本で3日だけやる気になる。現実ではジムの会費がもったいないと悩むくせに、分厚いハードカバーを片手に筋トレする矛盾も厭わない。ちなみに、読書中の「ちょっと休憩」が2時間の昼寝に化ける現象は、重力の法則と同じく普遍的真実である。
インテリのフリ道具
世の中には「本の見た目で人格を演出する」人種が存在する。カフェでドストエフスキーを広げるも、実はInstagramの更新が主目的だったりする。とはいえ、電子書籍リーダーは中身がラノベでも外見はクールなので、偽装コスパは抜群だ。ちなみに、本当の教養人は「あの本の何ページにそう書いてあった?」と質問されると、突然トイレに行きたくなる。
積ん読の生態学
未読本が山積みになる「積ん読」は、一種の希望の貯金だ。「いつか読む」という妄想は、貯金が「いつか使う」と妄想するのと心理的に同根である。統計によれば、購入後1ヶ月で読まれない本の運命は、クリスマスツリーの1月のようなものらしい。
本の虫の生存戦略
読書の最大の敵は「続きが気になるけど眠い」というジレンマだ。解決策は二つしかない。徹夜して翌日を台無しにするか、夢の中でネタバレを阻止するか。ちなみに、電車で乗り過ごすほどの没頭力を「集中力」と呼ぶか「社会生活の破綻」と呼ぶかは、あなたの銀行残次第である。

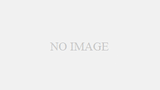
コメント