外国についての完全に偏見だらけのガイド:笑って学ぶ世界の歩き方
はじめに:外国とは何か?
「外国」とは、簡単に言えば「日本ではない場所」です。しかし、”日本ではない”というだけで、なぜそんなに人々は興奮するのでしょうか? 「海外旅行に行ったことがありますか?」と聞かれて「いいえ」と答えると、まるで「Wi-Fiがない生活をしていますか?」と聞かれたかのような反応が返ってくるあの感覚。でも安心してください。このガイドを読めば、あなたも外国について何でも知っているふりができます。
外国には、「行ったら人生変わるよ!」と熱狂的に勧めてくる人と、「海外は汚いし治安も悪い」とビクビク警告してくる人の2種類がいますが、真実はその中間あたりにあります。つまり、「人生変わるけど、財布も軽くなる」のが外国旅行の現実です。
さあ、世界への扉を開きましょう……ただし、パスポートとクレジットカードは忘れずに。
第1章:外国の人々 – 誰が一番変わってる?
1. アメリカ人:「大きいことがすべて!」
アメリカ人は何でも大きいのが好きです。ハンバーガー? 「ダブルバーベキューエクストラチーズメガサイズ」。車? 「小型トラックくらいのSUV」。病院の請求書? 「一生働いても払えない金額」。アメリカでは、笑顔とチップ(=お金)さえ忘れなければ、誰とでも友達になれます。「How are you?(調子どう?)」と聞かれたら、絶対に「Actually, I’m a bit tired…(実はちょっと疲れてて…)」などと答えてはいけません。「Good!(元気!)」とだけ答えるのがルールです。
2. フランス人:「あなたはバカ?」が挨拶
フランスに行ったら、店員さんに無愛想にされても動揺しないでください。「ボンジュール」と言わなかった客は人間未満というルールがあります。パリのカフェで「すみません、コーヒーを…」と日本語で話しかけると、「Pardon?(は?)」と冷たい目で見られます。「Excusez-moi」と言うのもダメ。「Bonjour, un café s’il vous plaît.(こんにちは、コーヒーください)」と言えないと、永遠に無視される呪いにかかります。でも、一度でもフランス語で話せば、突然優しくなる魔法がかかるので不思議です。
3. イタリア人:「ジェスチャーが言葉より強い」
イタリアでは、言葉より手の動きのほうが重要なことがあります。「マンマ・ミーア!」と叫びながら腕を振り回している人がいたら、それはただピザを待っているサインかもしれません。イタリア人の「5分」は「50分くらい」を意味し、「まもなく到着します」は「来ないかもしれない」という暗示です。でも、食事が運ばれてきた瞬間、すべての不満は消えます。だって、イタリアのパスタは神様が作ったくらい美味いからです。
4. イギリス人:「天気と紅茶で会話が成立」
イギリス人と会話するときは、「今日は雨ですね」で始まり、「紅茶に入れるミルクの量」で議論が白熱します。「How are you?」と聞かれたら「Not bad.(まあまあ)」と答えるのが正解。「絶好調!」なんて言ったら怪訝な顔をされます。 また、イギリス人は行列が大好きで、1人でも並んでいると、誰も何も聞かずにその後ろに並び始めます。「何の行列ですか?」と聞くのは社会的にNGです。
5. ドイツ人:「ルールは絶対、ユーモアは……」
ドイツでは、信号が赤なのに道路に誰もいなくても絶対に渡りません。たとえ深夜3時で周りに誰もいなくても、です。一方で、ビールに関しては世界一柔軟で、「ビールは朝食の飲み物」という文化があります。ドイツ人が冗談を言うと、10秒後に「あ、今のはジョークでした」と解説が入ることもあるので、すぐに笑わなくても大丈夫です。
第2章:外国の文化 – こうすればバカにされない
1. チップ地獄(アメリカ編)
アメリカでは、「チップを払わない=人間失格」です。レストランはもちろん、タクシー、ホテルのベルボーイ、トイレの attendants(!?)までチップを要求してきます。「15~20%が相場」と言われますが、実は「端数計算が面倒だから20%でいいや」という適当な理論が蔓延しています。
さらに、「カウンターで注文するだけの店」でも画面に「チップを選択してください(15%/18%/20%)」と出てきて、0%を選ぶと店員に睨まれるという恐怖体験が待っています。アメリカでは、「No tip = 悪魔の所業」なので、覚悟しておきましょう。
2. インドの「Yes」は「Maybe」を意味する
インドで「明日できますか?」と聞くと、「Yes!」と即答されます。しかし、これは「絶対できる」ではなく「多分ね!」くらいのニュアンスです。「すぐです!」=「1時間後かも」、「問題ありません!」=「実は超大問題です」ということがよくあります。これは「相手をがっかりさせたくない」文化のためで、悪気はありません。だから、インドでは「Exactly when?(具体的にいつ?)」**と何度も確認しないと、予定が空中分解します。
3. 北欧の「沈黙は金」カルチャー
フィンランドやスウェーデンでは、公共交通機関で他人と話しかけることは「犯罪」に近い行為です。バスで隣に座った見知らぬ人と目が合ったら、「死んだ魚のような目」で見返すのがマナーです。「最近寒いですね」なんて言おうものなら、「この人は狂っている」と疑われます。しかし、一度でも友達になったら、サウナで裸の付き合いをすることもあるので、距離感が難しいのです。
4. 中東の「時間はアラーの采配」
中東では、「会議は3時から」と言われたら、実際に始まるのは4時半くらいです。「もうすぐ着きます」は「まだ家にいます」の意味です。時間に厳格なドイツ人が中東でビジネスをすると発狂するという噂は本当かもしれません。しかし、アラブの伝統的なおもてなし(コーヒーとデーツを何度も勧められる)を受けると、時間の流れがどうでもよくなります。
第3章:外国旅行あるある – あなたも経験する悲喜こもごも
1. 「トイレ問題」は国際的トラウマ
-
- フランス:有料トイレが多い。「0.50ユーロ払って用を足す」というシステム。
-
- イタリア:駅のトイレは「使用不可」か「トイレットペーパーがない」の二択。
-
- インド:トイレットペーパーではなく「左手と水」が主流。ウォシュレット派には地獄。
-
- 日本:海外から来た人は「ウォシュレット神!」と叫ぶ。
2. 「日本だと当たり前」が通用しない
-
- レストランで水が無料で出てこない(ヨーロッパでは「ミネラルウォーター(有料)か?」と聞かれる)。
-
- 駅にゴミ箱がない(ヨーロッパではテロ防止のため撤去されていることも)。
-
- 電車が時刻表通りに来ない(イタリアでは「遅れるのがデフォルト」)。
3. 誰もが通る「観光客あるある」
-
- 「Hello! Thank you!」しか言えないのに現地人と会話した気になる。
-
- 「この現地支払い方法、どうやるんだ…?」と混乱する(特に中国のAlipay/WeChat Pay)。
-
- 「日本ではこうなのに!」と内心イライラするが、帰国したら「海外の方が良かった…」と懐かしむ。
まとめ:外国は面白い…でも、家が一番
外国は確かに楽しいです。でも、「海外は素晴らしい! 日本はダメだ!」と言う人も、「海外は不便! 日本最高!」と主張する人も、どっちも極端でしょう。本当のところ、「どこに行っても人間はちょっと変で、文化はバラバラで、それが面白い」のです。
だから、外国に行くときは、「変なところも含めて楽しむ」のがコツです。イタリアの電車が遅れても「まぁ、仕方ない」と笑えるかどうかで、旅行のストレスが激変します。
そして、結局は「日本のコンビニの便利さに気づいて涙する」のが日本人のサガです。
Happy travels! (ただし、荷物はスリに注意)

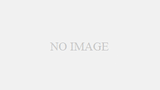
コメント