5とは
5とは、4の次に来る自然数であり、人間の指や足の指の数として、やたらと身近な存在だ。テストの点数としては、真ん中あたりだが、評価としてはまあまあ、といったところか。
数学界の凡人代表
数学の世界では、素数だったりフィボナッチ数列に出てきたりと、それなりに肩書きはあるものの、10や100のような桁数のボスには遠く及ばない。むしろ、「5の倍数」として、キリの良い数字になるための踏み台にされることが多い。お隣の4が「不吉」とか言われる中、特に悪評もなく、地味に頑張っている健気なヤツだ。
日常生活における存在感
日常生活では、5時、5分、500円玉など、やたらと顔を見せる。また、学校の成績で「5」を取ると「おっ!」となるし、5段階評価の「5」は最高点。と思いきや、なぜか5点満点のテストでは、5点取れて当たり前、みたいな雰囲気になる。この辺りの評価基準の曖昧さが、5の奥深さ…いや、適当さと言えるだろう。
五感の頼りなさ
視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚。人間は「五感」に頼って生きている、と言われるが、その信頼性は意外と低い。特に空腹時の「何でも美味しく感じる五感」や、酔っ払いの「判断能力が著しく低下した五感」は、全くアテにならない。にも関わらず、「五感が狂った!」と叫ぶあたり、人間は5に全幅の信頼を置いているフリをしているのかもしれない。
五人組の法則
なぜか色々なグループや編成が「五人組」になりがちだ。戦隊ヒーロー、アイドルグループ、バンドなど。これはおそらく、多様性を保ちつつ、多すぎず少なすぎず、人間関係が一番ややこしくなりにくい人数だからだろう。ただし、5人集まると、意見が5つに割れて収集がつかなくなる、というリスクは常につきまとう。
数の世界のモグラさん
5を制する者は、テストの平均点を制する!?いや、多分違う。でも、日常に潜む5の存在を意識すると、ちょっとクスッとできるかもしれない。

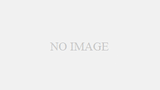
コメント